メッシュワークゼミと書くことについて(Yuto Kawabata)
書くという行為は、メッシュワークゼミの活動といつも絡まり合うように存在していた。
応募時の志望理由、discordでのつぶやきと応答、メモ、フィールドノート、この振り返りレポート。最後のゼミ展はテクストに限らない自由な形での表現を推奨されていたが、私は結局、エッセイ、日記、セルフライナーノーツなど、文章をメインとした展示を行った。
読んでは書いて、話しては書いて、聞いては書いて、歩いては書いて、考えては書く。書いているうちに、また新しい考えが頭に浮かび、次の言葉を書き出していく。
芋づる式に引っ張り出されてくる思考の先を辿っていくうちに、いつの間にか、さっきとは違う場所に立っている。書き出された言葉を眺めながら、浮かび上がってくる問いを抱えて、再びフィールドに向かったり、フィールドで記録したものを読み返したりしてみた。

ゼミの序盤から比嘉さんと水上さんは、人類学的なフィールドワークにおける書くことの重要性と、その性質について語ってくれていた。それをきっかけに、私たちゼミ生は思い思いに文章を書き始めることになった。
現場ではメモを取るので精一杯でも、ノートにまとめるときは箇条書きではない文章として書くことが大切。文章にすると、書き手の認識や解釈が入り込み、文体や引用の仕方などの細部にも、その人がどう捉えて、どう考えているかが表れる。それは民族誌・エスノグラフィーを書く手触りを知る一歩にもなるはず。/DAY3-2|メッシュワークゼミナールの記録(2023/09/30)
自ら考えたテーマを持ってフィールドに出るようになると、どれだけ客観的な記述をしようと努めても、自分の認識や解釈が入り込むのは避けられないことを実感した。
フィールドのできごとを箇条書きでメモしていくことは難しくないが、文章にしようとすると、背景にある構造や文脈を理解しなければ、何も書けないことに気づかされる。後から編集することを考えると、見るべきものや聞くべきものは膨大な量になり、記録する対象は、自分の関心に従って自然と絞られていく。
ノートとして編集する段階では、自分の書く一行一行すべてに対して、常に異なる解釈と表現の可能性が存在していることを知る。その上で、もっとも確からしいものを選んで、他のものを書かないまま進んでいく。
そんな風にして、メモとノートを書く、どちらの手つきにも、自分特有のものの見方が表れてしまう。

見落としてきたものや、書き損ねてしまったことは、当然ながらどの文章にも残されていない。数時間のできごとをノートにまとめようとしても、書けることは、私の身の回りで起きていたことのほんの一部でしかないことを、身をもって知った。
一方で、自分が受け取りさえすれば、わずかな記述の中にも、時間や空間、関係、感覚など、さまざまな要素を織り込めることも分かった。一回ごとのノートは不完全な記述ではあっても、何度もフィールドに通い、積み重ねていくと、その分だけ立体的なイメージが、自分の頭と文章の中に立ち現れるようになった。
ゼミ展へ向けて制作を始める際には、それまでのノートとは違う表現を模索する必要があった。1万字超の記録をそのまま読んでもらうのは難しい。短い言葉で伝えることを考えたとき、フィールドワークで感じた子どもと大人の関係の豊かさを表すのには、詩の言葉がふさわしいと思った。
まだ多くの文脈をまとっていない意味の開かれた音に近い言葉、身体性を意識させられる響きとリズム。コミュニケーションの道具としての役割に縛られない詩の言葉であれば、親子の言葉の質感に迫れるのではないかと考えた。
ただ、詩を書いたことは一度もなく本番に間に合う気はしなかったため、自分に書ける範囲で詩に近づきうるものとして、エッセイのような形の文章を書いてみた。
最終的には10篇のエッセイに加え、フィールドノート、制作日記、(『マリノフスキー日記』のことを思い出して途中から書き始めた)、セルフライナーノーツという、それぞれに少しずつレイヤーの異なる複数の文章を展示として並べることになった。
いずれもメッシュワークゼミがなければ書くことのなかったタイプの文章だと思う。後から読み返すと恥ずかしくなりそうな文章も多いが、そのくらい自分を差し出さないと、フィールドワークとゼミを通じて受け取ったものに対して、何か釣り合いが取れないように感じていた。

展示最終日に開かれた講評会では、比嘉さんから「育児や発達心理といったフレームで捉えることも、それを拠り所としてストーリーテリングすることもできたはずだが、寄りかからずに、見たもの、感じたもの、考えたことを誠実に言葉に紡いでいたのがよかった」というコメントをもらった。
また、展示を観てくださった研究者の方が、「知ったような概念でまとめてしまわないで、ともに経験する中でわからなさを味わうことが醍醐味なのだな」という感想をSNSに投稿されていたのを読んだ。
捉えどころのない制作物に対して、作り切った達成感はありながらも自分でも何が成果なのかはよく分からないと感じていたため、お二人の言葉は嬉しかった。それと同時にそうした態度こそが、私がメッシュワークゼミで学んできたことだったのだと再認識した。
既存のフレームや概念に回収せずに表現していく試みは、“名づけないまま書いていく”ような作業だったと思う。
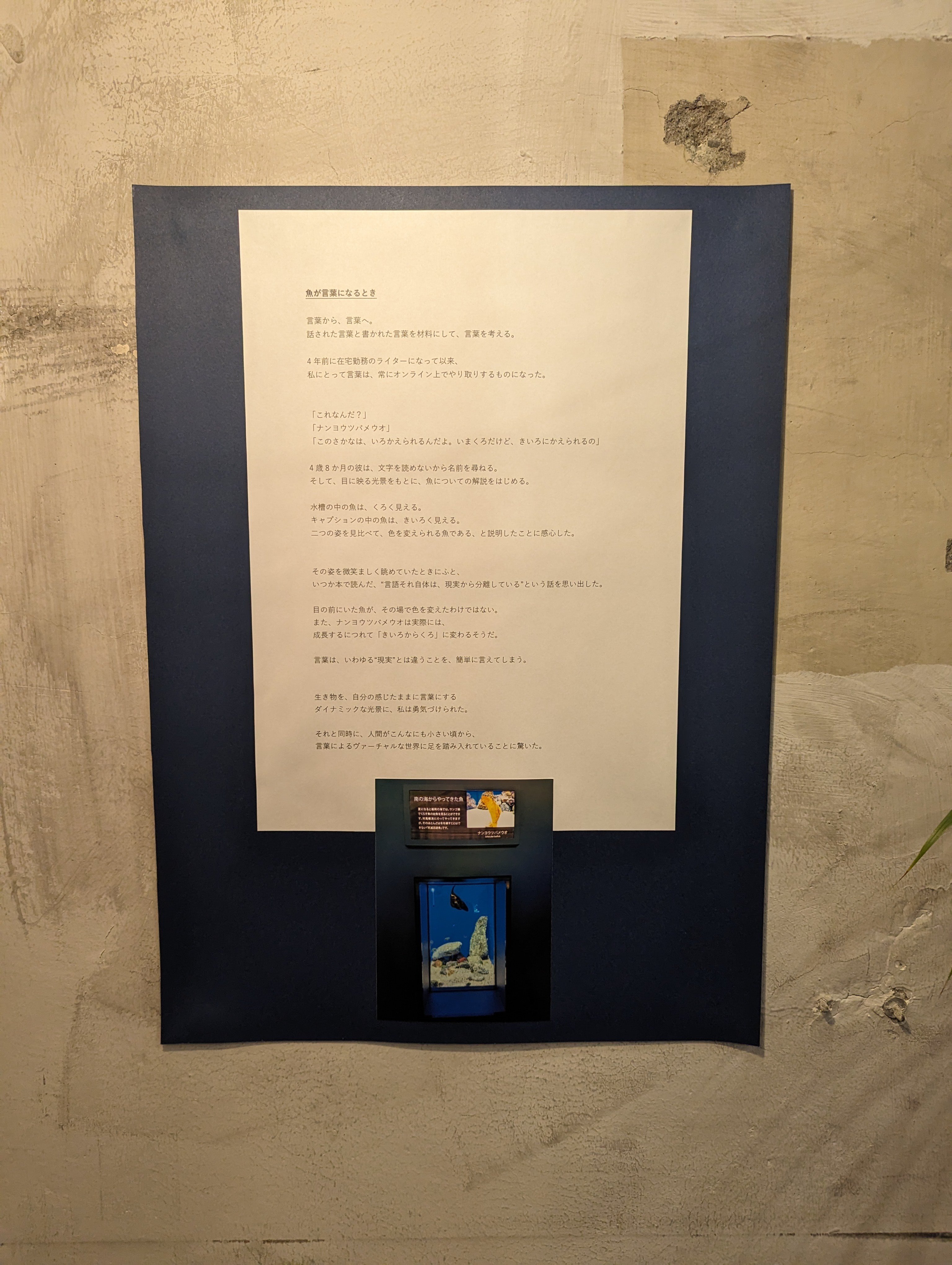
最後の1on1で、はじめて経験する私的な制作作業に、戸惑いつつも楽しさを覚えていることを話したとき、比嘉さんが「人は受け手と作り手、両方になれる」という話をしてくれたことがとても印象に残っている。
展示会場では、知らない人である私が書いた、これまた知らない人である私の友人たちについての話を、なぜか面白がって読んでくれる人たちがいた。
しばらくは、身を乗り出したり手に取ったりして、私がフィールドで見たものとじっと向き合ってくれた人たちの姿を思い出しながら、書くこと、作ることを続けてみよう思う。
